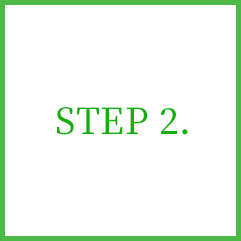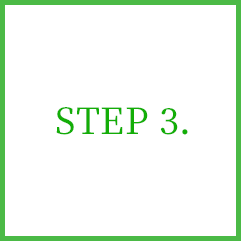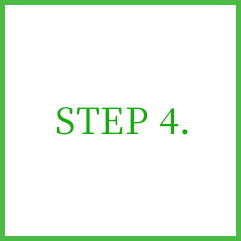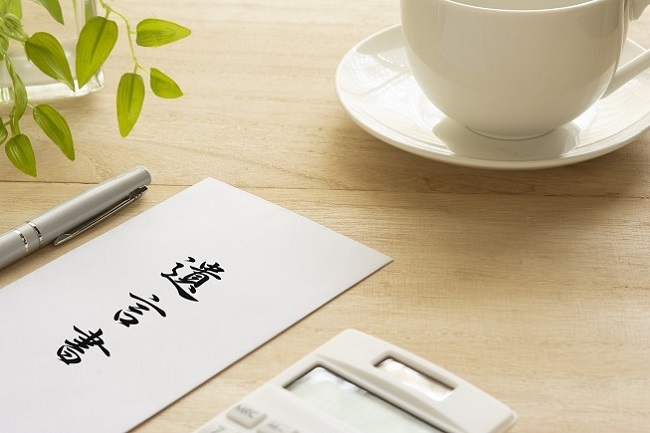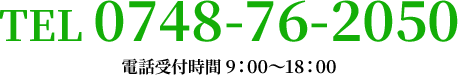相続とは、一定の身分関係にある人に亡くなった人の財産移転することです。相続はプラスの財産だけを相続し、マイナスの財産は相続しないということはできません。
マイナスの財産が大きく相続したくないという場合は、「相続放棄」や「限定承認」という申立てを家庭裁判所に行う必要がございます。
相続のために行政書士大黒たかお事務所では、相続人による遺産分割協議書を作成したり、予め被相続人が遺言書を作成します。
以下で必要な手続きや手続きの流れをご紹介します。
※当事務所では、相続による不動産登記手続きを行うことが出来ませんが、信頼できる司法書士と提携し、手続き支援をさせて頂きます。